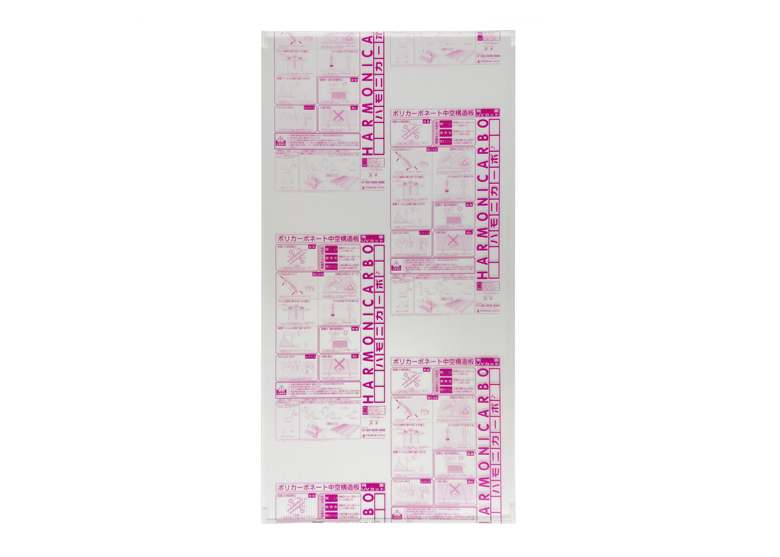【DIY】ホワイトボードシートを勉強部屋の壁に設置

息子がまだ小さいころ、リビングに「お絵かき用」として壁掛けホワイトボード(スチール製)を設置していました。
お絵描き卒業後は、ひらがな・カタカナなどのお勉強用、学校からのプリント(月の予定表、時間割など)を貼っておく場所などとして長らく活用してきましたが、さすがに高校の勉強のアウトプット用に使うには、サイズも小さく設置場所も低く(未就学児が書ける高さで設置したので)不便なので、新しくしました。
実は設置したのは5月頃の話なのですが、数か月使ってみて調子が良いので材料や設置方法などについてまとめてみました。
ホワイトボードシート
新しく購入するにあたり、コスパと合わせて「不要になった時に捨てやすい」というポイントを重視しました。今のホワイトボードはスチール製のガッチリとしたもの(60×90cm/3.5kg)なので、粗大ごみ扱いなのです。
そこで今回はホワイトボードシートを購入することにしました。
楽天などで検索するといくつかヒットしますが、
- 磁石がつく(マグネット対応)
- 壁に貼れる(裏面が粘着面)
- ある程度のシートに厚みがある(ペラペラは貼りづらい)
であることを条件にしました。
購入したのはこちら。
サイズは息子の希望もあり、やや大きめの90×150cm。これを勉強机の横とリビングの壁と2か所設置予定で購入。
商品はしっかりした筒状のクラフトパックで届きました。これならそう簡単には配送途中で凹んだりしないと思います。(90×150を2枚購入したので荷物も2個口で届きました)
商品購入ページに重さの記載はなく、届いたホワイトボードシートのみの重さを量り忘れてしまったのですが、思っていたよりずっしり。(完成品総重量は後述)
開封時に若干プラスチック系の匂い(裏が粘着面なので接着剤の匂いかも)がありましたが、開封後1~2日で気にならなくなりました。(恐らく国産ではない)
Amazonで探すならこちら『ホワイトボードシート』
下地を何にするか
さて、このホワイトボードシートをどうやって壁に設置するか?
弱粘着で壁面へ直接貼れる…と商品説明にはありますが、我家の壁紙は若干凹凸があるので直貼りはナシ。(シートを剥がすときに壁紙が一緒に剥がれるの怖いし、文字を書いた時にデコボコしてるのはイヤ)何かにホワイトボードシートを貼ってから壁面に…ということになります。
壁紙に凹凸がなく、ホワイトボードシートの厚みがある程度あればダイレクトに貼っても文字が書きにくい…とはならないかもしれません。ただし「今ある壁紙に直貼りしてもきれいに剥がせる」を信じるかどうかはクチコミを読んで判断。賃貸の場合は特に慎重に。
総重量(ホワイトボードシート+下地)はなるべく軽くしたいけれど、文字を書くときに凹凸感があったり、ペコペコするような下地ではだめ。
プラダンは安くて軽いけど文字を書くときにフワフワする?指で押しても簡単に凹むしなぁ…。薄いベニヤ板・アクリル板・MDF材だと重いかな?などいろいろ考えて、最終的にはポリカプラダン(= ポリカーボネート製のプラダン。中空ポリカーボネート板、中空ポリカ、ポリカ中空ボード とも)にしてみることにしました。
我家が購入品はこちら。ホームセンターに行けば3mm厚のものは1枚2,000円チョイぐらいで買えます。(他商品名では『ツインカーボ』AGC製 厚み:4mm~ などがあります)
我家が購入したものはこちら。
ハモニカーボ HC-001/クリア 910*1820 厚み:3mm アクリサンデー(株)
合板やアクリル板などは加工しにくく重かったので却下。ポリカプラダンならカッター(大型のほうが楽)で好きな大きさに切れて軽量(購入品『ハモニカーボ』3mm は 約1kg/枚)ですが、通常のプラダン=ポリプロピレン製(PP)に比べ硬度があります。
下地にシートを貼る
さて次はホワイトボードシートを下地(ポリカプラダン)に貼って行きます。床に置いて2人がかりで作業しました。
- ポリカプラダンに保護シートが張ってあるのでそれらを剥がす(裏表2枚)
- ポリカプラダンの上にホワイトボードシートを置き、位置決める
- ホワイトボードシート粘着面側の保護シート(ブルー)を少しづつ剥がしながら、端から空気を抜き圧着(やわらかい乾いたタオルで窓を拭くように)
※ホワイトボードシート表面の透明な保護シートはつけたまま - 余った不要な下地(ポリカプラダン)をカットする ※カッターは大型のほうが加工が楽
ホワイトボードシートは下地に貼り付ける前に予め平らにして丸まったクセをとることはしませんでした。多少クルンとはしていましたが、シートに厚みがあり硬めでしっかりしているので圧着途中で気泡が入ったり皴になったりせず、スムーズに貼ることができました。スキージーは使っていません。
枠(フレーム)の取り付け
ポリカプラダンをカットした面がそのままだと触った時にチクチク痛い(特にコーナー部)ので、ホームセンターで、配線カバー(ケーブルカバー、配線モール、ケーブルモールとも呼ばれる)を購入してきました。
配線カバー/1号/ホワイト マサル工業 ※高さ0号(8.8mm)~1号(10mm)あたり
マガリ/1号/ホワイト マサル工業 ※直線と号数をあわせてお好みで
配線カバーは上下のパーツに分かれているので壁に固定した時のビスも隠せておすすめです。
コーナーパーツ(マガリ)不使用・45度加工なしで垂直にカットしただけですが、私はあまり気にならないです。(使い始めれば枠だけをじっと見る事も無いので)
配線カバーを代用して枠を取り付けることで、カットした断面や角のチクチクを隠す(完全ガードではないものの、ちょっとした時にふれてしまうことは軽減される)ことができます。
枠があれば、小さい子供のはみ出し防止(勢いあまってシートから壁紙にはみ出ちゃった!)にもなりますね。
この後、壁面へのビス打ちの時に枠も取り付けるので、上下のパーツを付けたまま四辺のサイズにあわせてカットだけしておきます。
はさみで切れる?
加工が楽といっても、ホームセンターで購入した配線カバーは通常のカッターやハサミでは簡単には切断できませんでした。
専用のものは「モールカッター」と呼ぶそうですが、我家は折りたたみのハンディのこぎり(目が細かいもの・クラフトのこぎりなど)や剪定ばさみ(ホームセンターで購入した、刃が半月状にカーブしていてある程度の太さの枝ぐらいまで切れるもの)でカットしました。
目の粗いのこぎり使用時はモール切断面のバリに注意。気になるならやすりがけをするか、マガリ(コーナー用パーツ)で断面を隠すようにすること。
また、100均の剪定ばさみはアタリ/ハズレあり。基本的にはあまり切れないものが多いので、おすすめはしません。
工具類を新しく購入したくない場合は、下でご紹介する「ハサミで切れる」と記載のある商品をおすすめします。
100円ショップでも買える?
100均のダイソーには「ハサミで切れる」と説明書きのある配線カバーが売っています。ホワイトボードシートの大きさによっては継ぎ足しになりますが、気になる方は店頭でご確認を。(他100円ショップは未確認)
サイズ的には幅が12mm・高さが8mmなので配線カバー0号と同等ですね。「枠」として使うとなると継ぎ足して全長90cmで110円です。
他、ネットでざっと見た感じでは「切れるモール」は~1mの商品ばかりなので、枠の大きさによってはこちらも要:継ぎ足しとなります。
専用フレーム
ネット検索では専用のフレーム( ホワイトボードシート用フレーム @ホワイトボードプラザ楽天市場店)も売っていました。フレームを薄くシンプルに仕上げたい場合は、専用のフレーム(シルバー)を購入をおすすめします。
粉受け(下辺)
絵や文字を書くのがメインの場合、ホワイトボードマーカーで書いた字を消すとカスが出ることもお忘れなく。※消しカスの出ないタイプのペン使用時を除く
我家は4辺とも配線カバー(1号)で枠にしました。厚みが1cm程度しかないので消しカスを受けきれず床にも少し落ちますが、枠はプラ素材なので掃除もさっと水拭きするだけです。
きちんと消しカスをキャッチできるように幅を出したいのであれば、下辺にアングル(L字型のパーツ)を取り付ければ粉受けとして代用、ペン/イレーザー置き場としても利用できそうです。
アングルは樹脂製のものが配線カバーと一緒にモール売り場などにあると思います。
アングル(樹脂製) 光モール
本体の重さ(設置前の完成品)
ホワイトボードシート(90*150cm/厚み0.8mm)+下地(ポリカプラダン90*150cm/厚み3mm)+枠(配線カバー4辺/幅17.5mm・高さ[厚み]10mm)で、総重量は 4kg 弱でしょうか。(体重計でアバウトに測定)
以前のスチール製の物よりもサイズは倍以上大きくなりましたが、重さ的にはちょっと重くなったかな?ぐらいです。
※ホワイドボードシートにあわせてポリカプラダンはカットして使っています
設置方法(壁面へのビス打ち)
壁への設置手順は以下のとおり。こちらも2人で作業をしました。
- ホワイトボードシート表面の保護シートを周辺だけ少し剥がし、配線カバーの位置を決めて、数か所ほど両面テープで仮止め
- 壁の中のスタッド(間柱)を見つけて配線カバー(下)の上から本体をビスで固定
※設置場所に応じて石膏ボード用アンカーなどを別途購入 - 配線カバー(上)をセット、枠の出来上がり
こうしてホワイトボードシート+下地+配線カバー(下)の上からビス止めすると、ホワイトボードシート+下地の本体がビス打ちの力加減で凹むことも防止でき、最後に配線カバー(上)をはめるとビスも隠れ、ちょうどよい枠になります。
賃貸などで壁に穴を開けたくない場合は、ラブリコ や ディアウォール のような(2×4材のつっぱりパーツ)などを利用してみてはいかがでしょうか。
ホワイトボードマーカー
ホワイトボードシートのオマケでついてきたマーカーもありましたが、消し心地が悪かった(跡が残るほどではないが、さっと消えなかった)ので、別途購入しました。
購入したのはこちら。パイロットのボードマスターという商品です。
パイロット ボードマスター @ビックカメラ ※1本~購入可・送料無料
油性顔料(アルコール系)インクは直液カートリッジ式。直液式はインクがダイレクトにペン先に伝わるのでインクがなくなるギリギリまで使えるのがメリットです。
また、セットされたカートリッジはインク残量が見えるデザインになっているので交換時期がわかりやすく、本体の半額ほどで買えるのでランニングコストも良いです。もちろんペン先が潰れてきたらペン先だけ交換可能。
ハッキリむらなく書けて、すっきり消える。とても気に入っています。
ちなみに、2か月前に書いた文字もさっと綺麗に消えました。
シート表面の経年劣化などで徐々に書いた跡が残りやすくなるかもしれませんが、ひどい汚れは無水エタノールでのお掃除が紹介されていたので、気になり始めたらやってみたいと思います。
イレーザー(ホワイトボード消し)
今はオマケで付いてきたものを使っていますが、過去使ってきたイレーザー(ホワイトボード消し)で1番良かったのはこちら。コクヨ めくれるホワイトボード用イレーザー メクリーナ16です。
コクヨ めくれるホワイトボード用イレーザー メクリーナ16 @ビックカメラ ※送料無料
使い続けていると消しカスで黒くガサガサになり性能が落ちてくるのですが、その面を「1枚めくって新しくする」というもの。16層のミルフィーユ状になったシートをめくる作業も楽しく、おまけに中だけ(16層のシート)の入れ替え可能!と、非常に優秀です。
※品番/サイズ(RA-32:M/RA-31:Lサイズ)と対応する替えシートをご購入下さい
コクヨだけではなく、他社もしくはホームセンターオリジナルブランドなどから似たような「1枚めくって更新」できるイレーザーもあります。
めくれない普通のイレーザーの場合は、ケースから取り出しやさしく水洗い(汚れがひどい場合は中性洗剤を使って)すると、ある程度はきれいになります。表面が毛羽だってきたら新しいものに交換を。念のため、洗う前に商品のパッケージの注意書きやメーカーの公式サイトの商品紹介ページでご確認ください。
完成品:使い勝手はどうか

設置後のちゃんとした写真を撮る前にどんどん書き込まれてしまったので、画像は最後に剥がすべき保護シートがまだ貼ってある状態のホワイトボード。(サイズ:90*150cm)
ホワイトボードシート+ポリカプラダン(下地)+配線カバー(枠)で作ってみましたが、コスパ良し・軽量で加工/設置しやすくおすすめです。
下地のポリカプラダンが中空構造なのでちょっと心配(文字を書くときのフワフワ感)でしたが、材の硬さもあり書きづらさ・違和感はありません。書いた文字もよく消えて使いやすいです。(シートとペンの相性も良し)
我家では「書く」ことがメインなのであまり気にしていませんが、やっぱり磁石のくっつく力が、今までのスチール製ホワイトボードと比べ弱いと感じます。
学校からのプリント類は、家にあった磁石(100均のネオジム)で、A4を3枚重ねまでは大丈夫でしたが4枚はアウト。イレーザー(マグネット内臓)は、商品によっては重みでずり落ちてきてしまい、なんとか枠で止まっている状態です。
※小さいお子さんが使う予定なのであれば、マグネット類は誤飲の危険があります。特にネオジム磁石は磁力が強く大変危険です。
まとめ:2か所の設置費用
- ホワイトボードシート(90*150cm)×2枚 @楽天
- 下地 = ポリカプラダン(92*182cm) ×2枚 @ホームセンター
- 枠 = 配線カバーで代用(光モール #338/182cm) ×6本 @ホームセンター
※壁面設置用のビスは手持ちのものを使用
※ホワイトボードマーカーなどの備品類は手持ちがなければ購入
コストはだいたい1ヶ所(1枚)10,000円、2か所に設置で約20,000円でした。
必要なサイズにもよりますが、大きなポリカプラダンや長いモール材などは近所のホームセンターで買ったほうが送料を気にしないで必要な分を購入できたので、ネットで買うより安かったです。
不要になった時は分解して全て通常ゴミ(プラなど分別は必要)で捨てることができ、このサイズのスチール製やホーロー製のホワイトボード(枠や脚付き)を買うよりも安く設置できました。
あとはいつまで綺麗に使えるか。下地のポリカプラダンが「たわんで」こないか?
しばらく使ってみて、シート表面の劣化具合など、後々気づいた事が出てきたらメモを追記していきたいと思います。