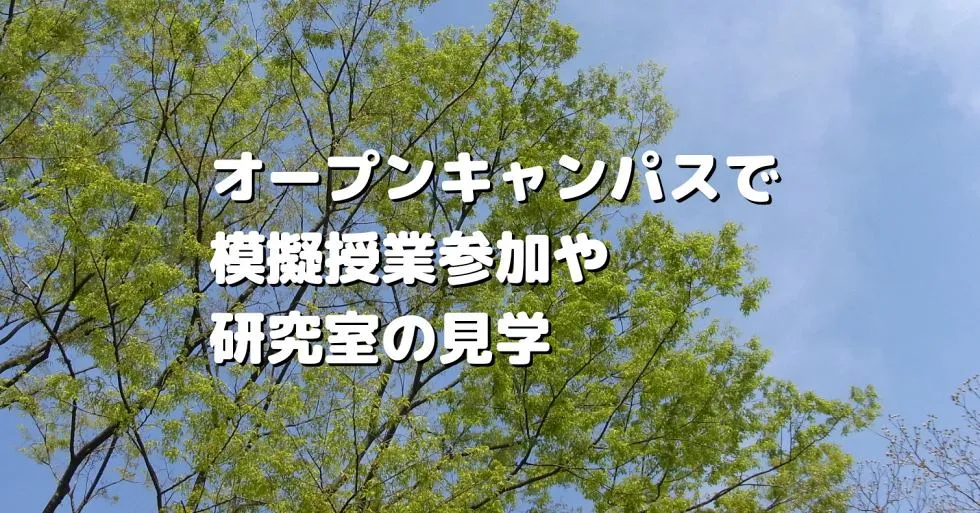【高2夏】大学のオープンキャンパスへ

7月あたりから部活・夏期講習の日程表を確認しつつ予約を入れていた、夏の大学のオープンキャンパスへ行ってきました。高2の今年は3校です。(5校予約を入れて2校キャンセル)
ただ、行ってみたい大学(志望校を決めるうえで見ておきたい大学・モチベを上げるために行きたい大学)のオープンキャンパスが8月上旬あたりに集中していたので、部活・夏期講習とあわせると、かなりのタイトスケジュールでした。
オープンキャンパスって行く必要ある?
オープンキャンパスに行かなくてもパンフレットを見ればだいたい分かるんじゃ…と思う方もいるでしょう。オンラインオープンキャンパスという形式を用意している大学もあります。ただ実際に参加してみると「パンフレットだけじゃ分からなかったこと」は多くあるように感じます。
文系・理系で考え方(行く必要があるかどうか)が違うかもしれません。
私大理系志望の我家にとっては、自分(子)が興味のある分野(学科)を見つけるために、とても有意義なイベントでした。※特に研究室見学
また、キャンパスツアーで案内してくれる学生スタッフさんとの会話など、対面でないと得られない「何か」は、勉強に対するモチベーションアップに繋がるのですよね。親がうるさく勉強!と言うより効果が高いです。
かと言って、遠方に住んでいるので日程の調整がつかない・予約が取れなくて行けない…ということもあるでしょう。オープンキャンパスの参加/不参加が直接合否につながるわけではありません。他の方法で自分に必要な情報を集めましょう。モチベーションは自分次第です。
予約とキャンセル(キャンセル待ち)について
キャンパスツアー・模擬授業などのイベントは要予約の大学が多く、予約開始後すぐ満員になってしまいます。6月ごろから夏のオープンキャンパスの案内が出始めるので、予約開始日時・予約の要/不要・実施イベントは必ず事前確認をしておき、まずは予約を入れましょう。
オープンキャンパス参加アカウントの作成
本人予約時に同伴者(保護者など)をあわせて予約できる大学と、本人・同伴者が別々にアカウントを作成して個々に申し込む必要がある大学があります。事前にアカウント登録しておけるシステムなら、予約開始前にアカウントの作成だけしておくと手続きがスムーズに進みます。
特に一度満席になった後のキャンセル枠の予約は1秒を争うので、メールアドレスなどはコピペ入力(もしくは辞書登録)できるように準備しておきましょう。
LINEで大学のアカウントを友達登録して申し込むというスタイルもありました。
キャンセル待ちはできるのか
我家が申し込んだ大学ではキャンセル待ちができる大学はありませんでした。基本的にはイベント開始ギリギリまでスマホでこまめに空き状況を確認・空きがあったら申込み=参加可能となります。
行けなくなったらキャンセルは必要か
オープンキャンパスに行けなくなってしまった場合のキャンセル手続きについて(要/不要・キャンセル方法)は、予約完了後に送られてくる大学からの案内メールを確認します。大抵の場合は、登録したオープンキャンパスアカウントのマイページより手続きをすることになると思います。
キャンセル手続きが必要なら、当日でもキャンセル手続きを。特に模擬授業や実験などの体験イベントは空きが出るのを待ってる人がいるかもしれません。
スケジュールの一例
去年は理系とだけ決めてこんなスケジュールで見学してきたので、こちらの記事をご参考まで。(誰と行くか・どんな服装で行くかなども書いています)
学部・学科までほぼ決まっているという人は、学部・学科説明会やキャンパスツアーを省き、模擬授業・実験などの体験会への参加・研究室見学をメインにして、じっくり見て回るのもおすすめです。受験にむけてモチベーションを上げていきましょう。
受付時に、登録アカウントマイページの「参加証」の提示が必要な場合があります。事前にスマホでスクショをとっておくと便利ですよ。
1日何校ぐらい行けるか
第一志望であれば1日かけてじっくり見学することをお勧めします。(私達が行った大学は16:00終了でした)
併願校(滑り止め校など)の場合であれば、オープンキャンパスならではのイベント(学部・学科説明会・キャンパスツアー・模擬授業など)に1~2個参加(半日で全部は無理です)をするとして、移動距離があまりない前提で、午前/午後で各1校で1日2校が限度ではないかと思います。(昼食の時間もお忘れなく)
パンフレット集めと大学の立地確認(イベントには特に参加しないで個人で構内を見て回る)だけなら、3校ぐらいは行けるかもしれません。
でもこれなら夏の暑い時期にわざわざ行かなくても良さそうな…(個別のキャンパス見学はいつでもどうぞという大学が多いです ※年末年始や試験期間中など一部の期間を除く ※個人見学には案内役はつかない ※校舎内への立ち入りはできない場合が多い)
学食や売店(生協)も行ってみよう
午後からのスケジュール的に一度外へ出てお昼を食べている時間がなかったので、我家は大学内の学食でささっと食べました。オープンキャンパス中はメニューが一部に限られている場合も多いですが、外で食べるより早くて安いのでは?
学食の営業開始直後(我家が参加した大学では、ほとんど11:00~営業でした)が狙い目なので、前後の参加イベントの開始/終了時間を確認して、ぜひ早めの昼食を。学部・学科説明など大人数が参加できるイベントが終了した直後にとどっと混みます。
売店では大学のオリジナルグッズの他、赤本を特別価格(オーキャン特別価格:10% off)で売っていたり、大学ブランドのペットボトルの水 ¥100~110 (例:早稲田の水・慶応の水・ソフィア水・理大水など)もあります。
2024年夏のオープンキャンパスを終えて
去年(高1)は理系とだけ決めていた状態でなんとなく参加しましたが、今年のオープンキャンパスを通じて学科(できれば気になる研究室もピックアップ)を絞る事ができればいいなと思っていました。
また今年は、理工学部・理学部の化学系の学科も視野に入れて参加。(去年は工学系中心に見学)去年に続き、今年も多くのものを得ることができたと思います。
【解決】物理をどうするか
恐らくどこの高校でも同じような流れだと思いますが、公立高校だと高2の夏休み前に高3の選択科目の仮希望を提出して担任の先生との面談があり、その後三者面談(秋には高3選択科目の最終決定 ※以降変更不可)が控えていると思います。
夏の面談では「ある程度早い段階で見切りを付けて受験科目(化学)だけを勉強したい」という現実的な気持ちと「大学に入ってから必要となる科目(物理)を高校で学んでおく。※ただし受ける大学によっては受験科目として必須ではない」という理想の間で気持ちが揺れ、理科の2科目目の選択に悩んでいる(化学ともう1つどうするか)と相談しました。
受験に不要な科目を選択してしまえば、最低限とはいえ定期テスト勉強が必要だし、受験科目の勉強だけに集中することはできません。
我家は私大志望なので、理科が2科目受験になるのは難関大だけなんですよね…。志望校としてリストアップできるほど、これから学力が上がるのかどうかは微妙なところ。
とはいえ、担任の先生(数学の先生)の体験談も交えると、やはり物理はとっておいたほうが良いというお話。大学では「高校で習っている」という前提で授業が進むため、工学系に行くなら必須。化学系に行くにしてもやっておくべき。との事でした。(高校の理科の先生に相談すると良いのかもしれません)
この件、大学の学科説明でも参考になる話が出ました。
化学系学科の模擬授業でしたが、高校までの暗記系化学と違って、大学では化学と組み合わせて数学も物理も必要になります。化学が好きでこの学科にしたいけど数学苦手・物理苦手という人は高校で頑張って勉強してきてくださいね。というお話でした。
X(旧Twitter)で「化学科」で検索すると、化学を理解するために物理・数学が必須。高校までの化学とは別世界。という言葉を多く見かけました。
バイオ系の学科には行かないから生物はいらないなんて、そんな程度の認識だったのですが、中高校でいう「理科」の各分野は、学びが深くなる大学では数学も含め複雑に関係しているのですね。
現段階では化学科・応用化学科・工学系ということで学科も1つに絞っていないし、物理は高校で学んでおいたほうが良さそうです。(最終的に物理を受験科目として使わなくても・工学系に進まなくても)
【解決?】受験する学部・学科をしぼる
理系は確定。学部もほぼ確定(理工学部 or 大学によっては理学部)なのですが、学科がまだ迷っています。工学系・化学系、現状どちらも捨てがたい。
模擬授業や研究室見学をした中で、この研究室があるからA大学は化学系。この研究室があるからB大学は工学系がいいな。と大学によって興味のある学科が違うのです。
でも、よく考えたらそもそも志望を1学科に絞る必要もないですね。先述したように、理科の選択科目は「どちらにいっても大丈夫」なように選択した(勉強するのは大変ですが)ので大きな問題はありません。
※ただし、化学系(化学科/応用化学科)なら受験は化学指定
これから学力がどれくらい上がるか。その上で今後本人の興味がどちらかに傾くこともあるかもしれないし、別の道が出てくるかもしれない。志望大学はまだ確定する必要はないので、もう少しいろいろ情報を集めじっくり検討させたいと思います。
目標にむけて
今年の夏もオーキャン参加でモチベが上がり、夏休み中にコレやるぞ!と気合が入っておりましたが、いつまでこの状態が続いてくれるのか。(高1の時はしばらくするとスイッチがOFFになってしまいました)
今は親世代の大学受験の認識とは大きく異なり戸惑うことも多いですが、受験するのは本人。最終的には本人が興味を持って学べる大学へ無事行けると良いなと思います。